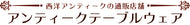西洋のガラスと明治の工匠
文明としてのガラス
明治時代、西洋文明に遅れないようにということで、数多くの実用書が出版されていました。
「洋食独案内」という明治19年(1886年)に東京で発売されたこの雑誌も、そんな中の1冊でした。
ちょっとしたテーブルマナーや、料理などを主に紹介している雑誌なのですが、付録としてビリヤードのことまで説明した冊子です。
これは、アメリカ人の婦人たちが口伝したものであると言われています。
この雑誌では、洋食も文明の素晴らしいひとつであると認識されているのです。
ということは、洋食器もそんな文明のカケラとして数えられるのではないでしょうか。
たとえ真似であったとしても、西洋のガラス食器やランプなどを安価に作ることは、当時の日本にとって良しとされていたものでした。
まだこの当時は、デザインやスタイルの借用というものに、世間がおおらかであった時代なのです。
鉛ガラスとソーダ石灰ガラス
屈折率が高く、カットの細工などもしやすい鉛を含むガラスは、現在では高級ガラス素材のイメージがあります。
しかし、明治時代中期頃までの日本において、多量に鉛を含むガラスは、単なる技術上の問題のひとつとしか考えられてはいませんでした。
鉛ガラスや「苛性硝子」の2種類は、原料にソーダ灰を使用しているガラスに比べると品質が劣ってしまっていました。
そのため、売れ行きも悪く、総生産額も当時で1/10ほどでしかなかったのです。
もっとも、大部分は欧米のガラスと同じようにソーダ石灰ガラスへと変わってはいたのです。
これらのことから、ガラス製造に関して、火力とガラスの質というのが何よりも大切であったということがわかります。
鉛ガラスは明治28年にもなると、すでに過去の材料として扱われていました。
このことを踏まえてみると、江戸時代に作られていたびいどろガラスと、明治中期以降のガラスを見てみてください。
両者はその材質の違いから判別することが可能となります。
びいどろというのは、多量の金属を含んだ鉛を使用していることが一般的でした。
その証拠に、びいどろの器を指ではじいてみると、金属のような音が響くのです。
なぜならば、これは窯が小さいことや、木炭の低い火力を伝統的に使っていることなどが原因だったのです。
しかし、明治中期以降に一般的になったソーダ石灰ガラスは、窓ガラスなどに普通に使用されている素材ですから、同じように指で弾いてみても音が響くようなことはありません。
まれに日本で鉛を含んでいるクリスタルガラスが製造されていても、うつわの形状や加飾が時代によってまったく異なってきますので、判別することは容易にできるのです。
それだけではなく、成型や色のつき方などをみても、判別することは可能です。
一方で判別するのが困難なのは、江戸時代後期から明治初期にかけての作品です。
この過渡期にかけて作られた製品は、ガラスの年代を特定するのは困難となっています。
なぜならば、その時代に使われていたのはともに鉛ガラスだったからです。
時代は維新へとなり、変わっていったからとはいえ、急に江戸の技術がなくなってしまうわけではないのです。
日本の工芸は明治10年代頃までは、まだまだ江戸の雰囲気を残していました。
この過渡期に生産された、切子などの作品は、江戸にも明治にも見られるものでしたので、どちらの時代の作品であるのか浮遊している状態です。
さらにもっとも判別することが困難な時代があります。
それが、明治・大正のガラスと、欧米のガラスです。
なぜならば、この時代、日本の技師たちは欧米の製品を意図的に模倣していたからです。
見本として同じソーダ石灰ガラスを使用していますので、さらに混乱してしまいます。
これらの判別するためには、丁寧に成型の技術、ガラスの質、そして仕上げなどをチェックするほかないのです。
ほとんどの場合は、上質なものが欧米の作品。
そして若干粗いものが日本の作品というふうにわけられます。
しかし、まれに欧米の製品にも粗いものがあり、反対に日本の製品にも上質のものがありますので、やはり判断は難しいのです。
ガラスは陶器のように胎土の質や釉などを見て判断することができないのも、判断が難しくなってしまう理由ではあります。
どの工房で、いつどんな技法でどんな製品が作られていたのか。
それを知ることは美術史家の大切な商売道具でもありますが、それがなかなか困難なものなのです。
欧米製と日本製の区別
紀元前1世紀の終わり頃になると、ガラス成型に吹き竿が使用されるようになりました。
フェニキア人の工匠は、早く安くガラスを製造するために、この吹き竿を利用したのです。
これは、アルカリ含有量の高いソーダーガラスを管状の竿に取ります。
そして半球状に膨らませて成型するのです。
その後の西ヨーロッパでも、森にある樹木の灰を利用したカリを熔剤とするカリ・グラスも生まれました。
しかし、ソーダガラスは変わることなくイタリアを中心として、素材の主流であることに変わりはなかったのです。
16世紀のヴェネツィアでは、スペインやエジプトから、ソーダを輸入して製造をしていました。
イギリスで酸化鉛を添加する鉛クリスタルガラスが開発されたのは、17世紀の後半になってからでした。
この製法はオランダにも伝えられたのです。
しかし、これは高級な素材でカットなどを施すようなものでした。
一方、江戸時代の和製ガラスは、そのガラス調合を中国の宋代から引き継いでいました。
多量の金属鉛と、硝石に石粉を混ぜて低温で熔融するガラス種を使用していたのです。
明治前期になるまで、この製法が零細な工房で続けられていました。
しかし、鉛量の多いガラスは、壊れやすくて薬品の貯蔵には不向きでした。
日本に大切だったのは、輸入したガラスのデザインや形を真似ることだけではなく、石灰ガラスというガラス製品を製造するときの素材まで真似る必要があったのです。
そんな日本製のガラスが材料も欧米と同じになった明治中期以降、日本製と欧米製のガラスは見分けるのが難しくなってきました。
見分け方としては、たとえば日本製のプレス皿の場合、肌が荒れています。
さらにバリと呼ばれている、口辺の薄いガラス膜の処理が綺麗に出来ていないことが多いのです。
一方の欧米製は、再熔融のたくみさから、ツヤのある肌を持っています。
プレスコップの場合では、ガラス質が黒っぽく、気泡も目立ちます。
そして、小さなシワも目に付きますし、底部の研磨も雑になっていて、欧米製とは真逆の仕上がりなのです。
カット(切子)ガラスの場合、欧米製のものはパターンが複雑でカットの谷間も鋭くなっています。
そして1番の特徴は、ガラス素地の無色度が高く、純良なのです。
なにより、エッチングであっても、グラヴュールであっても、和製のものは、手馴れている感はあるものの、鋭さや深さに欠けているところがあります。
例外は当然ありますが、これらのようなことが主な判別の基準となってきます。
明治期には、高級品と呼ばれるものはすべて、輸入された製品で揃えられるようになりました。
そのせいもあり、江戸期に見られたような献上品的な日本製品は出現しにくくなったようでした。
どんな時代であっても、輸入されてくる美術工芸品や上質な絵画などを模倣するということは行われてきました。
それは、欧米でも日本でも変わりがありません。
たとえばマイセン窯が東洋の磁器を模倣しましたし、有田窯は景徳鎮磁器を模倣しました。
けれど、この模倣という行為は美術にとって決してマイナスなことばかりではないのです。
模倣することにより、新しい美術、芸術作品を生み出していくための基礎体力を養っていくことにも繋がるからです。
そして先の世になってからよく見聞すると、この模倣が時代や国、地域の様式などを見事に取り込んでその時代に溶け込んでいることに気づかされるのです。
明治・大正のガラスには、欧米のガラスというものは歴史の重みを感じることができる、とても大切なものでした。
主に手本としていたのは、理化学器具に関してはドイツの製品を。
ランプや食器類などは、アメリカ、フランス、イギリスなどでした。
この模倣という学習が、新しい製品を生み出すために必要なことだったのです。
現在では、この「本歌」と「写し」を見比べることにより、日本人の美的風韻を知ることができるようになるのです。
それを知ることで、先人たちの「創造」も同時に見ることができるのではないでしょうか。
明治時代の近代産業は、欧米の技術の模倣と伝習から革新を生み出す時代でもあったのです。
手工芸から産業工芸へと進化していく道でもありました。
しかし、これらのことは決して簡単なものだったわけではなく、その当時の工匠や企業家たちが焦燥にかられ、苦闘したきた歴史そのものでもあるのです。
その歴史を知らぬままに現代では、製品の批評をしてしまいますが、その歴史をしっかり知ることで、同じ製品を見ても、そこに含まれる想いや力を感じることができるのではないでしょうか。
手吹きの薬瓶
山崎豊太郎は明治の末年に理化学ガラスの工場を持つことになりました。
山崎が信州から上京してきたのは、明治9年のことです。
ランプ問屋だった上総屋に住み込みの奉公に入ったのです。
ガラス製造を覚えたのは、そこで運搬の仕事をしながらのことでした。
当時のガラス調合を振り返り、山崎はほとんどの場合、珪砂1、鉛2の割合だったと語っています。
鉛は、酸化鉛ではなくて金属鉛のまま調合をしました。
原価は高くついたようですが、そのほうが早く熔けたのだといいます。
山崎はガラスの吹きの技術を覚えました。
そして、岸田の精錡水という目薬の瓶や、北海道のウニを入れるための容器などを吹いたのです。
理化学ガラス工場を開くきっかけとなったのは、輸入品を真似して、試験管やレトルト(蒸留器)などを作ったことだったようです。
岸田の精錡水というのは、点眼薬のことです。
これを製造販売していたのは、岸田吟香で彼は明治前期の新聞記者でもありながら企業家でもありました。
そんな岸田が銀座に開いた薬局で販売していたものが精錡水なのです。
アメリカ人の宣教師であり医師でもあったJ・C・ヘプバーンが横浜に来日している際に、岸田は目の治療を受けています。
それがきっかけとなり、岸田は「和英語林集成」という和英、英和の辞典を編集する手伝いをすることになりました。
ヘプバーンのことを、当時の日本人たちは「ヘボン先生」と呼んでいました。
彼こそ、「ヘボン式ローマ字」を作り出した人でもあるのです。
このヘプバーンが考案した目薬は、瞬く間に人気商品となりました。
そのため、販売は日本国内だけではなく、中国にも店舗を出店し、輸出するようになったのです。
そのことから、目薬を入れるための薬瓶が大量に注文されるようになるのです。
東京にある工房のいくつかが、この注文を受けました。
最初に、この瓶の発注を受けた和吹きの工匠は、技術が未熟でした。
製品を100本仕上げましたが、底の部分の仕上げが拙く、満足に自立する瓶は仕上がった製品のうち、20本ほどしかなかったと言われています。
このような瓶は、鉛瓶であったと考えられています。
ちなみに、先ほどご紹介した岸田吟香の四男は、洋画家であり「麗子像」で有名な岸田劉生なのです。
ガラス工匠の修行
明治の後期頃に行われていたガラス工匠の修行について、少しご紹介していきましょう。
この頃のガラス製造家に小泉重蔵という人がいました。
彼は明治34年に浅草橋の近くにある加賀金というガラス工房に弟子入りをしました。
このとき、重蔵は12歳でした。
小さなルツボでガラスを溶かしていましたが、このときの燃料は、木炭、やはり鉛種だったのです。
仕事が始まるのは朝の5時。
朝食はひと仕事終えてからでないと食べれませんでした。
カンテラが灯をともす下で、夜の10時になるまで仕事は続いたのです。
休憩と呼べるのは、昼前の10時頃一服する時間、そして昼休み、三時のお茶の時間があっただけでした。
今では考えられない17時間労働だったのです。
自分の時間と言えるのは、寝る時間だけという有様でした。
しかし、新米の師弟は仕事だけこなしていればいいというわけではなかったのです。
誰よりも早く起床して、工場の中や外の掃除、使い走りや子守など、さまざまなことをこなさなくてはいけませんでした。
そのため、重蔵は朝のまだ暗いうちに起床して、小ツボの蓋を開け、ガラス吹きの練習をしたいたのだそうです。
7年にもおよぶ年季を終了し、そして1年間の礼奉公を済ませて、ようやく一人前になれるのです。
休みは、毎月1日と15日だけ。
年季中は、畳の上で座臥することは許されていませんでした。
そのため、生活は常に板の間だったのです。
祝日や紋日のとき以外は、どんなに寒い日であったとしても、足袋を履くことはできませんでした。
ガラス工場のこのような労働環境は、なんと大正5年頃まで続いていたのです。
重蔵は石炭の粉末を混ぜて褐色ガラスを作ることに、明治38年に成功しました。
そして明治45年、重蔵は妻を迎え、東京に工場を持つことができたのです。
このとき重蔵は25歳でした。
舶来吹きの習得
鈴木栄三郎は、象牙細工職人の子どもとして生まれました。
栄三郎の家は、東京にある日本橋で外国からの注文を受けて仕事をしていたのです。
そんな栄三郎はのちに、ガラスの大物づくりの名手と呼ばれるようになる人物です。
栄三郎は、本所にある小出兼吉のガラス工場に入ります。
明治37年。栄三郎が11歳のときでした。
このことで、当時の師弟が入門する平均年齢がわかるのではないでしょうか。
小出の工場で行われていたガラスの製造方法は、舶来吹きでした。
この舶来吹きというのは、鉄パイプにガラス種を巻きつけて息を入れるヨーロッパ人直伝の製法だったのです。
舶来吹きというのは、型を使用しません。
そのため、習得するには年季が必要であると言われていました。
作るときも、3人か5人が1組となり、呼吸をあわせて作業をおこなっていたのです。
鈴木が師弟であった頃、この作業に失敗してしまうと、1本11キロ以上もある重い吹き竿で、先輩から頭を殴られていたのだといいます。
このような過酷な状況の中で、鈴木は仕事を覚えていったのです。
しかし、鉄パイプで殴られる日々でしたので、頭からは血が流れ、生傷が絶えない毎日だったといいます。
鈴木は、小出の工場を出ると、17歳で本所の職長として玉木硝子に入りました。
このときの鈴木の給料は60円。
東大を卒業して役人になった人の給料が30円だった時代です。
鈴木の給料がいかに高額だったのかがわかるのではないでしょうか。
ガラス工匠の得る給料というのは、実力によって大きく差が出てきます。
鈴木は、大阪で径一尺二寸(約36センチ)、長さ二尺(約60センチ)の解剖瓶をなんと10個も吹き上げることができ、大阪の工匠たちを大変驚愕させたそうです。
重油窯から10貫ものガラス種を吹き竿に巻きつけて、樫の板木と息を駆使して大物の容器を吹き上げたのです。
鈴木が独立して工場を持ったのは、大正に入ってからでした。
利休コップと腐食
名工岩城瀧治郎は、江戸で有名なガラス工場である加賀屋の系譜沢定次郎の弟子としてスタートしました。
岩城が和吹きの技術をマスターしたのは、この場所でした。
それだけで満足しなかった岩城は、工場を出て最新の技術を得るために、官営品川硝子製造所の生徒募集に応募したのです。
そして、イギリス人の技師に師事し、舶来吹きを習得しました。
その後、明治15年にわずか25歳という異例の若さで職工長となったのです。
翌年には製造所を出て、独立します。
置物や、肉厚の大型瓶などを吹く舶来吹きを、この日本にいながらにして完成させたのです。
岩城は、この頃に松本徳次郎という工匠のいるガラス工場を訪れています。
このとき、当時の製造家と西洋の関わりがわかるやり取りをしているのです。
松本のもとを訪ねた岩城は、松本に海外にはゆで卵を半分に割ったような形のリキューというコップがあると教えます。
コップ作りをしていた松本は、早速このコップを作ってみるのです。
そしてステムを鎔着させたグラスを完成させました。
さらに、岩城の言うとおり「利休台付きコップ」として販売をします。
このグラスは、瞬く間に評判となり、人気商品となりました。
お察しのとおり、松本はリキュールと利休を間違っていたのです。
大正4年に発行されたガラスのカタログの中には「利久台付」「利久火切玉足」というものが確かに存在します。
このような、どこかのどかさを感じる話もあれば、反対に悲愴な話もあるのです。
当時、欧米で行われていたガラスの腐食を真似するために、日本では文様を表すため、硫酸を使用していました。
明治20年代に入ると、フッ化水素酸が使用されるようになります。
この頃のことです。
大阪の松田虎三郎は、フッ化水素酸の蓋を閉め忘れたまま、棚に陳列してしまいました。
すると、陳列棚に置いてあったガラス瓶が、すべて同じように白く腐食してしまったのです。
それを知った医師は大変驚きました。
そして、このままフッ化水素酸を使い続けていると、5年も経たないうちに肺まで腐食されてしまうと警告を出したのです。
それを信じた松田は、フッ化水素酸をすべて処分してしまいました。
そこへ、砲兵工蔽の彫刻師が訪ねてきます。
彼は、肺の病にかかっており、左の肺がすでに機能しない状態でした。
そんな状態であったのに、彼はいずれ腐るのであれば、薬品で腐っても、病で腐っても同じことであると言って、自ら進んでガラス腐食の仕事についたという出来事があったのです。
工匠として名を馳せた人たちは、ほんのひと握りに過ぎません。
しかし、そんな工匠たちの影には、彼らを支える人たちが大勢いたのです。
そのことを知ることで、明治・大正期のガラス製品は、さらに深みを増して見えるのではないでしょうか。
新しい時代
明治20年頃になると、東京の業者よりも先に大阪では、東南アジアや中国、インドに向けて、瓶、プレガラス、ランプといった製品を輸出し始めていました。
ガラスを海外に売りさばいていたのは、大阪の川口、本田、神戸、元町などにあった中国系の商館を通じてのことでした。
第一次大戦以降になると、日本の製品はヨーロッパ製品の代替えとして需要が高まるようになります。
そのことにより、東京の業者もようやく、輸出を行うようになりました。
明治末期になる頃には、輸出製品だけではなく、日本国内に置いてもガラスの消費が増えていきました。
日常生活の中で、ようやく日本もガラス製品を多く使用するようになったのです。
その中でも、実用品である板ガラスやプレスガラス、瓶などがメインとなっていました。
プレスに関して言えば、昭和に入るとガラスの質も均一のものとなったのです。
昭和13年に販売された「東京百貨型録」には、日本橋・佐々木商店が提供しているガラス器が掲載されています。
紫、青、赤、琥珀、水色といった薄い被せガラスに切子を施した皿、コップ、鉢、花瓶。
他にもスモークガラスといったものも掲載されています。
青色の被せ切子コップであれば、6個箱入りで1円50銭(4285円)、赤色コップ6個5円(1万4285円)、紫色コップ6個3円80銭(1万856円)、青色切子花瓶は1点5円となっています。
切子も高い価格になっていますが、赤のコップは青色の被せ切子コップに比べて3倍も高くなっているのが驚きです。
このような花切子を薩摩切子や大正ガラスと考えている人も、稀にいます。
しかし、このような色被せには大正ガラスにも薩切子にもない独特の雰囲気があるのです。
ガラス生地も良質なものとなっています。
昭和初期から13年頃まで製造がされていたこれらの色被せや、スモークガラスはとても高級品とされていました。
ですが、このような贅沢品は日本が戦争を始めるこの年以降には、製造することそのものが難しくなっていくのです。
佐々木硝子店が大正4年に発行したカタログに「硝子赤儘鉢」という三つ入れ小鉢(五寸、六寸、七寸)があります。
値段にして3点で86銭(約4000円)でした。
この価格というのは、吹きガラスにしては安価と言えます。
現在、この巻縁鉢は大変人気があります。
口辺は金赤であったことでしょう。
しかし、昭和13年の赤というのは、銅により少々暗い赤色であったと考えられています。
これは、家庭の中においても違和感のない、シックで上品な銅赤の食器が好まれていたからです。
昭和初期なると、ガラスの製造方法だけではなく色も変化しているように感じられます。
柴田化学は、深川に工場を作りました。
そしてその後、昭和30年に小型タンク方式を利用した、鎔融炉で超硬質ガラスの生産に成功するのです。
そのガラスはパイロガラスとこの当時呼ばれていました。
しかし、その後名称を玻璃の王様、ハリオと変えます。
超硬質ガラスはガラスポットとして愛用する人も少なくありません。
耐熱温度差150度あるので、ポットに適しているのです。
この超硬質ガラスを作るために必要な、鎔融には1600~1700の耐熱性が必要となってきます。
戦後、日本のガラス製造の技術はどんどん進化を遂げています。
この時代のガラスには、作家たちの個性や想いまでも溶け合って形となっているように思えます。