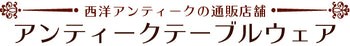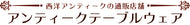ボーンチャイナってどんなのを言うの?
ボーンチャイナってどんなの?
弊社によく受けるご質問に、ボーンチャイナ(Bone China)と硬質磁器(ファインチャイナ(Fine China))の違いは何でしょうか?というのがあります。
オンラインショッピングの世界では、ボーンチャイナ(Bone China)と硬質磁器(ファインチャイナ)の区別に関して多くの誤解がございますので、その2つの違いを解説していきますね。
チャイナの意味を理解する
磁器を見ていくと、よく『チャイナ』と最後につきますが、これはそのまま中国という意味ではなく『磁器』という意味になります。
歴史を遡っていくと、ヨーロッパに初めて磁器が運ばれたのは中国からのもので、その磁器が中国から来たことによりヨーロッパの人々は、磁器のことをチャイナと言い始めたのです。
硬質磁器(ファインチャイナ)とボーンチャイナの違い
磁器を作る原料を見たときに、一般的なものが硬質磁器でありカオリン(粘土)、長石、珪石から作られています。
これが硬質磁器(ファインチャイナ)のことです。
ボーンチャイナは、イギリスでカオリンを見つけることができなかったために、その代わりに牛骨を入れて対応しました。
骨を英語でボーンって言いますよね。
だから、ボーンチャイナなんです。
Cow Bone Ash(牛の骨灰)
このように、作られる原料によって呼び方が変わるのですが時々
『ファイン・ボーンチャイナ』

というのを見かけると思います。
これは、牛骨の割合の違いであり普通のボーンチャイナであれば、30%の割合でファインが入ると50%になります。
そのことによって、ファインボーンチャイナはより硬く、より透き通った白さを実現できているのです。
磁器の作り方はこちらの動画でも詳しく解説しておりますので、興味のある方はご覧くださいませ😊
ボーンチャイナと硬質磁器(ファインチャイナ)の特徴
ボーンチャイナと硬質磁器(ファインチャイナ)の主な違いは、色にあります。

左側が硬質磁器を代表する『マイセン』の磁器の裏面になります。
右側がボーンチャイナ代表の『エインズレイ』の磁器の裏面になります。
マイセンの方が真っ白であるのに対して、エインズレイの方は同じ白でも、乳白色なのが特徴です。
また、この2種類の磁器には『透光性』にも違いがあります。
これはカップを光にかざしてみるとよくわかります。

このように、ボーンチャイナは硬質磁器(ファインチャイナ)に比べると、より光が透けて見えます。
どっちを選んだほうがいいの?
このように2つの異なる磁器を紹介してきましが、結局のところどっちがいいの?
という疑問に行き着いたのではないでしょうか?
その答えはですね、全ては皆さんの趣向次第ということになります。
基本的にどちらの磁器も、品質に大きな違いはありません。
硬質磁器であれば、1350程度で焼結させるので非常に硬い磁器が完成します。
ボーンチャイナの方は、1250度と硬質磁器と比べると100度程度低くても焼結できるので、色が飛ばず自由な色彩が可能です。
しかし、表面には軟釉という硬質磁器とは違う釉薬を使うために、ナイフなどの傷が食器に入ることもあります。
とは言っても、かなり力を加えない限り傷も入りませんので、自分の気に入った方を選んでいただくのが正解なのかぁ、というのが私の心情です。